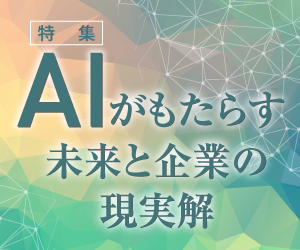AIを軸に再び人が集まるシリコンバレー
石野:今回はどのような目的で渡米されたのでしょうか。
福田:今回の渡米の目的は、日本に進出を検討している企業や我々が注目している企業に直接会って話を聞くことです。また、Dreamforceに合わせて集まるSalesforceの元同僚など、これまで共に働いてきた幅広い業界で活躍している人たちと会い、最新動向を掴みに来ています。
一時期はシリコンバレー一極ではなく、ニューヨークやテキサスなどさまざまな都市にテクノロジー企業の拠点が広がりましたが、AIを契機に、世界中の優秀な人材が再びシリコンバレーへ集中している実感があります。公開されている最新情報は日本でもすぐに確認することができますが、ここにいないと入ってこない情報が、確かにあると感じています。

石野:米国において、AI関連のテクノロジー企業の動向をどう見ているのでしょうか。
福田:今のAI市場は、インターネットで言えば90年代後半にネットスケープなどが時代の寵児として注目されていた頃に近いと思います。Googleがようやく産声を上げたくらいの段階です。SaaSで言えば2000年代前半に相当し、投資家にとっては面白い局面ですが、ユーザー視点でベットすべき企業が明確に存在するかというと、私はかなり慎重に見ています。それくらい競争と進化が早いのです。
石野:オンプレミスやSaaSの時代と比較して、どのような変化が起きようとしているのでしょうか?
福田:オンプレミスの時代は、予定通りシステムが稼働するかなど不確定要素が多い中で、ハードウェア、ソフトウェア、システム構築費用をすべてユーザーが一括購入し、その後も継続的に保守費用を払わなければならない時代でした。
そこでオンデマンドというモデルが登場しました。今のSaaSの原型ですが、必要なユーザー数の分を使いたい分だけ月額料金制で利用する形態です。しかしこれではベンダー側の経営は安定せず、十分な先行投資もできません。
この課題を解決するために、SaaSの普及期には複数年契約や利用料の一括前払いという契約形態の変化が起こりました。また解約を防ぎ、LTVを拡大するためのリソースとしてカスタマーサクセスという役割が登場しました。
今起きている大きな変化は、これまでのSaaSが業務プロセスの効率化により人の生産性を向上させる目的であったのに対して、AIエージェントは直接的に人の代わりに仕事を実行できるという点です。
AIの導入においては、今まで以上にPoCで進めるケースが多いですが、これは人を採用する時に試用期間を設けるのと似ています。人であれば簡単に解雇はできませんが、AIエージェントであればSaaSのように最初から複数年契約をせずに、期待通りの成果を上げなかった場合や他に良いソリューションが見つかった時にすぐにスイッチする選択肢を残しておきたいと顧客は考えるでしょう。時代の転換点において、顧客の検討プロセスにも変化が現れるとみています。
石野:この数年でユーザー数によるシート単位の課金からコンサンプションによる課金形態も増えてきましたが、AIエージェントの世界では料金体系にも変化は出てくるのでしょうか。
福田:そう思います。例えばカスタマーサービス系のAIソリューションでは問い合わせを完了した件数など成果指標による課金や、プロジェクト単位で金額を決定するなどの例も見られます。従来のソフトウェアライセンスから、よりサービスに近い考え方へシフトしていくでしょう。