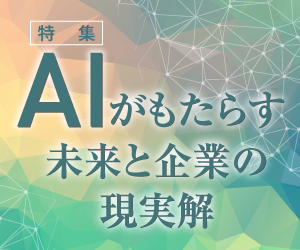M365、Salesforce、ServiceNowとも連携
(上部写真は「Gemini at Work」で「Gemini Enterprise」を発表するサンダー・ピチャイCEO)
これまでの生成AIツールが個別アプリケーション内での効率化にとどまっていたのは、企業の実際の業務プロセスが複数システムに分散している現実を捉えきれていなかったためだ。営業担当者が顧客対応を完結させるには、Salesforceで商談情報を確認し、ServiceNowで過去の問い合わせ履歴を調べ、OutlookやGmailで関連部署とやり取りし、最終的にMicrosoft TeamsやGoogle Meetでミーティングを設定する、といった複数システムにまたがる作業が必要となる。Gemini Enterpriseは、この「システム間の断絶」という構造的課題に正面から取り組んでいる。
事前に開かれた説明会でグーグル・クラウド・ジャパンの寳野雄太氏は「本来人間が期待したいのは、単一アプリの中での機能向上だけではない」と指摘する、企業の業務プロセスは複数のアプリケーションやシステムにまたがって展開されており、エンド・ツー・エンドでの業務完結が重要だと強調した。

今回の発表によると、ServiceNowやSalesforceから顧客対応履歴や商談情報をコンテキストとして取得し、関連部署とのメールのやり取りも踏まえて、チームミーティングの招待を自動作成する。さらに「マーケティング・メディアエージェント」を呼び出し、社内の商品情報に基づいて、Googleの画像生成モデル「Imagen」を使った製品画像を自動生成することなどが紹介された。
企業では、商談や社内情報や顧客に関する様々なコンテキストをもとに「次はどう行動するか」ということを常に考え、選択している。そしてそのコンテキストは、Gmail、Google Driveだけでなく、Microsoft 365のSharePoint OnlineやOutlook、Salesforce、ServiceNowなど、あらゆる場所に存在する。Gemini Enterpriseの特徴は、Google製品に依存せず、これらすべてをコンテキストとして活用できる点にある。

Gemini Enterpriseは5つの主要コンポーネントで構成される。第一に、Geminiモデルをエージェントの頭脳として即座にアクセス可能にする。第二に、「Agent Designer」と呼ばれるワークベンチを提供し、技術者でなくても自然言語でエージェントを構築できるようにする。第三に、研究からコーディングまで専門性の高いGoogle製およびパートナー製のエージェント群を用意する。第四に、あらゆる場所に存在する企業のシステムおよびデータをコンテキストとして接続する。第五に、すべてのエージェントを視覚化し保護する包括的なガバナンス機能を備える。
寳野氏は、企業のコンテキストはあらゆる場所にあり、それは単にGoogle製品だけではないと述べた。GoogleのサービスであるGmail、Driveだけでなく、MicrosoftのM365、SharePoint Online、Outlookといったサービスをコンテキストとして利用できることは企業にとって大きな意味があると説明した。認証にはEntra IDも利用でき、この点でもGoogle Cloudのエコシステムに依存しない設計となっている。
AgentspaceからGemini Enterpriseへ - ワークベンチとモデルの緊密連携
従来から発表されていたAgentspaceとGemini Enterpriseの違いは、Geminiモデルと「ワークベンチ」(Agent Designer)のより緊密な連携にある。ワークベンチでは、技術者でなくても自然言語でエージェントを構築できる。寳野氏は、このワークベンチとGeminiモデル、そしてエージェントのスイートが緊密に連携する形で、今回パワーアップさせた点が重要だと述べた。

パーソナライゼーションとナレッジグラフ - 企業専用の「理解」を自動生成
Gemini Enterpriseの差別化要因の一つが、企業・ユーザーごとに最適化されたパーソナライゼーション機能だ。同プラットフォームは「ナレッジグラフ」技術を活用し、企業専用のナレッジグラフを自動生成する。寳野氏によれば、これによりエージェントは企業の階層構造やチーム構成、最近のメールやチャットのやり取りをコンテキストとして認知し、より的確な行動を取ることができるという。
たとえば、「○○さんとミーティングを設定して」という曖昧な指示でも、組織構造と最近のやり取りから適切な相手を特定し、ミーティングの詳細を補完して予定を作成する。この「文脈理解」が、単なる作業の自動化と真の業務支援を分ける境界線となる。
データ活用の観点では、「データサイエンスエージェント」がプレビューとして提供される。これは自然言語でビジネスユーザーがデータドリブンな洞察を得られるようにするもので、接続されたデータソースだけでなく企業のビジネスコンテキストも考慮して分析を行う。専門的なデータ分析スキルがなくても、「2025年の売上傾向を分析して」といった指示で、適切な分析手法を選択し結果を提示する。
開発者ガバナンスとコーディングエージェント
開発者向けには「コーディングエージェント」が含まれる。これはGemini CLIを基盤とし、エージェントと協働しながらコードを作成するバイブコーディング(Vibe Coding)を実現する。社内の設計図などもコンテキストとして考慮し、スプリントをエージェント内で回して、最終的な動作確認まで行う。レガシーコードのリファクタリングや、新しい環境への移行作業なども支援する。
これらの機能はGemini Enterpriseのサブスクリプションに含まれており、従量課金ではなく使い放題として提供される。従来の生成AIサービスでは、利用量に応じた課金が企業の導入障壁となっていたが、定額制により社内での積極的な活用を促進できる。

ガバナンス機能も強化されている。エージェントの利用権限と共有権限を一元管理し、どのエージェントを誰が利用できるか、そのエージェントがアクセスできるデータは何かを厳密に制御する。マルチエージェントシステム全体にわたるAI固有の組み込みガードレールにより、個人情報の自動ブロックやプロンプトインジェクション攻撃の検知など、すべてのエージェントのやり取りを保護する。寳野氏は、集中管理ダッシュボードからすべてのエージェントの可視性と制御を実現し、IT部門が安心して展開できる環境を整えていると説明した。