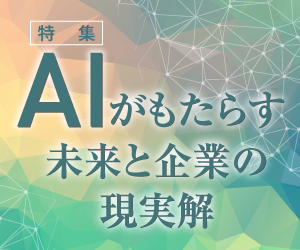IT企業ですら難しいAIエージェント活用 リアルな試行錯誤を共有
生成AIが登場して以来、私たちの働き方は急速に変化しました。多くの企業が、生成AIの導入を進めています。しかし、現場で耳にするのは「導入したものの活用が定着しない」「思ったほど使われていない」といった声です。
AIの導入が目的化し、成果に結びついているのかわからないという感覚──これは私たちも同じでした。IT企業である私たちでさえ、AIエージェントを現場に根づかせるために、多くの試行錯誤を繰り返しています。
本連載では、私たちが経験した成功と失敗のプロセスを率直に共有します。AIエージェントとどう戦略的に協働していくか、読者の皆さんが具体的に考える一助になれば幸いです。
役員から新卒1年目まで巻き込む AI浸透を後押しする空気づくり
サイバーエージェントグループのAI変革の第一歩は、2023年9月にさかのぼります。ChatGPTの登場から数ヵ月後、社長の藤田(晋氏)より全社員に次のメッセージが発信されたのです。
AIをめぐってはさまざまな論点がありますが、業務効率化で成果を上げることは疑いようがありません。今後はAIを徹底的に活用した企業が、活用が遅れた企業に大きな差をつける時代になる。そう確信しています。
この言葉を合図に、グループ全体で「2026年までにオペレーション業務を6割削減」という目標を掲げ、AI活用が本格始動しました。そして、さらに動きを加速させるために、2023年10月には全社横断の専門組織「AIオペレーション室」を設立。以後、実運用のAIエージェントが社内で次々と誕生しています。
全社を挙げた取り組みの一つが「生成AI徹底理解リスキリング」です。役員から新卒1年目まで、全レイヤーを対象に生成AIを学ぶ機会を設けました。この取り組みの目標は、全社員が「生成AIによって業務効率化の効果や新規事業の着想を得られる状態」となること。生成AIおよび大規模言語モデル(LLM)の概要や、生成AI活用における法務・セキュリティの基本も含めて、実務で活きるAIリテラシーの底上げを図りました。
「受講が進まない」「受けても使われない」ケースが珍しくない全社施策にもかかわらず、受講率は99.6%(約6,300名)。なぜここまで定着したのか。理由は次の2つです。
(1)役員も受講を必須とし「全社共通の目的」を明確化:生成AI活用の意義とKPIを示し、毎週の役員会議で進捗をレビュー。トップから学ぶ姿勢を示した
(2)全社メディア/社内サイネージで継続発信:「盛り上がっている」「皆がやっている」という空気を意識的につくった
これらは、当社のカルチャーに合った工夫であり、もちろん、すべての企業に同じ手法が適合するわけではありません。それでも、自社の文化に照らし合わせて、転用可能な要素があるのではないでしょうか。