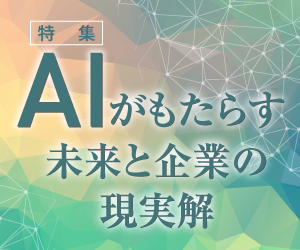誰でもAIとつながれる“本当の民主化”へ
心を感じるAI──。その実現を目指すのが、AI研究者の大澤正彦氏だ。人間のようにあらゆるタスクをこなす汎用人工知能「AGI(Artificial General Intelligence)」、人とAIの関係性を研究する「HAI(Human-Agent Interaction)」の2つを専門分野とする。「具体的にいえば、誰もが認めるような“ドラえもん”をつくりたい」と語る大澤氏。心があるように思えたり、友だちになれたりする。そんなAIを、世の中に浸透させようとしている。
そこで重要となるのが、同氏の研究分野であるHAIの考え方だ。従来、人はソフトウェアやロボット、コンピュータ自体を進化させようと奮闘してきた。これに対して、HAIは人とAIを一体として捉える。
「わかりやすい例が、豊橋技術科学大学の岡田美智雄名誉教授が研究する『弱いロボット』です。たとえばショッピングモールのごみをなくしたい場合、利用客に直接ごみの持ち帰りや削減をお願いしても、実際に取り組んでくれる人は少ないでしょう。だからといって、全自動ごみ捨てロボットを開発するにしても、技術的ハードルが高い。そこで、ごみを拾う能力自体はないごみ箱型ロボットをつくるのです。ごみがうまく拾えず困っているロボットを見た人が、自然とロボットを助けようと動き、結果的に利用客がごみを拾うようになる。このように、人とAIが歩み寄り、ともに課題を解決するのがHAIの考え方です」

現在、ビジネスの現場でも、ChatGPTをはじめAIを業務に取り入れる人が増えている。しかし、期待するアウトプットを得るには、適格なプロンプトの入力などコツが必要だ。使いこなすのは容易ではない。これが、AI活用の二極化を生んでいる要因の一つともいえる。
そこでHAIの考え方が浸透し、AIが人の心を感じたり、引き出したりする存在になれれば、誰でも直感的にAIと関われるようになる。あらゆる人が最先端のテクノロジーにアクセスできるようになり、AIの民主化が加速するというわけだ。
ただし、実現においては、AIが人の意図を理解できなければならない。一般的に浸透しているAIでは、言葉と発言者の意図が異なる“皮肉”など、まだ人の意図を読むのは難しいのが現実だ。この課題を解決するために、大澤氏の研究室では、脳の情報処理の仕組みや人間の振る舞いを再現する実験を行っている。
「以前、人間の脳の働きを模倣した機械学習であるディープラーニングに、記憶を司る海馬の神経接続の仕組みを適用したところ、まさに人間の海馬とよく似た反応が見られました。それ以来、人間の仕組みを真似れば、人間のように振る舞うAIが実現できるかもしれないと考えています。最近では、人間が相手の意図を読むときの情報処理の方法を真似ることで、大規模言語モデル(LLM)の意図を読む能力を向上させられると示しました」
このような研究は、そのままビジネスにおける新たな価値創造に応用できるという。AIが人の意図を読み解く能力は、消費者との間に人間らしい関係性を築き、新しいコミュニケーションを生み出すからだ。
たとえば、ECサイトのレコメンドシステム。現在は、顧客の購入履歴や閲覧履歴から関連商品を提案する手法が主流だ。探している商品とまったく関係のないものが提案された場合、無視する、もしくはバグだと認識する顧客も多いだろう。
ところが、自分の友人や子どもが同じような提案をしてきたらどうか。多くの場合、「なぜこれをお勧めしてくれたのか」と聞いてみるなど、前向きな反応を示すはずだ。AIで同様の反応を引き出せれば、企業やブランドは今より挑戦的なレコメンドが可能となる。
「今までの科学は、1%の失敗で責められてきました。これからは、失敗してもポジティブな結果に変えられるのです」