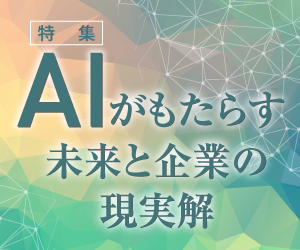AI活用を加速させる「CAIO」の設置実態と二極化
冒頭PwCのチーフ・AI・オフィサーである藤川拓也氏は、CAIOを「AI戦略の立案から実行までを統治し、社内外のステークホルダーとの連携を通じて事業価値創出とリスク管理(攻めと守り)の両立を担う経営幹部」と定義していると語った。

PwC Japanグループチーフ・AI・オフィサー兼データ & AIリーダー 藤川琢哉氏(左)
PwCコンサルティング マネージャー 塩原 翔太氏(右)
調査結果によると、正式なCAIOを設置している企業は22%、CAIOという名称ではないものの同等の役割を持つ責任者を設置している企業は38%に達し、合計で60%の企業がAI推進の責任者を置いているという。
特筆すべきは、CAIO設置の有無が企業のAI成熟度に決定的な差を生んでいる点だ。CAIOまたは同等の責任者を設置している企業は、未設置企業と比較して「業務領域」「技術領域」「管理領域」のすべてにおいて、AI活用推進度が20ポイント以上高い。

成果領域で異なる「3つのCAIO類型」と最適人材
一口にCAIOといっても、企業が目指すゴールによって求められる資質は異なる。PwCコンサルティングの塩原翔太氏は、調査結果の分析から、成果を創出しているCAIOを以下の3つのタイプに分類した。
タイプ1:業務効率化を重視するCAIO
コスト削減やバックオフィス業務の効率化を主眼とする。既存の業務プロセスやコスト構造に精通している必要があり、CIOやDX責任者経験者が「社内登用」されるケースで成果が出ている。
タイプ2:新規ビジネス創出を重視するCAIO
AI技術を起点に新しい収益源やビジネスモデルを創出する。技術知見と業界知識の双方が不可欠であり、データサイエンスの専門性を持つ人材が適している。
タイプ3:AIの将来ビジョンを重視するCAIO
中長期的な競争力強化を見据え、全社的なAI戦略策定やガバナンス構築を担う。組織変革やチェンジマネジメントの専門性を持ち、CDO(最高データ責任者)経験者などが、外部から登用されるケースも見られる。
注目すべきは、「顧客体験(CX)の向上」においては、「管理領域×社外登用」のCAIOが最も成果を上げている点だ。既存の枠組みにとらわれない新しい顧客体験を設計するには、内部の論理に縛られない外部人材の視点が有効であることが見てとれる。