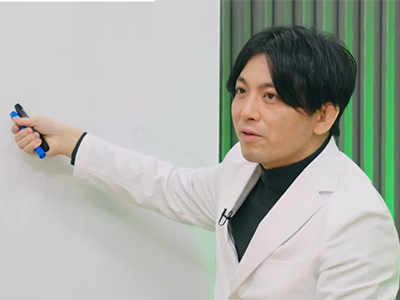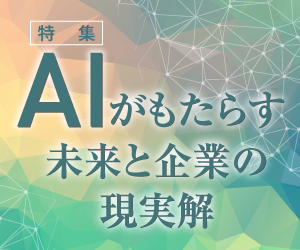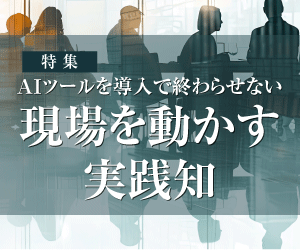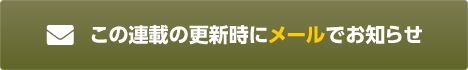会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

藤井有生(AIdiver編集部)(フジイ ユウキ)
1997年、香川県高松市生まれ。上智大学文学部新聞学科を卒業。人材会社でインハウスのPMをしながら映画記事の執筆なども経験し、2022年10月に翔泳社に入社。ウェブマガジン「ECzine」編集部を経て、「AIdiver」編集部へ。日系企業におけるAI活用の最前線、AI×ビジネスのトレンドを追う。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です