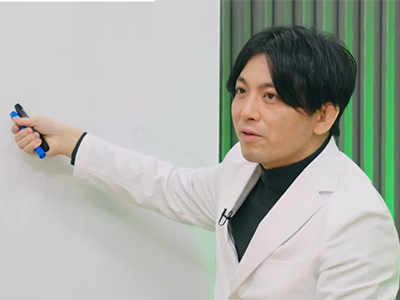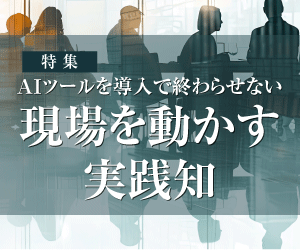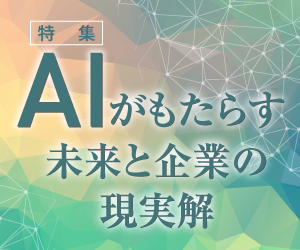会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
【新連載】全社員がAIに仕事を任せる勇気をもつには 失敗・改善から見えた文化醸成の道筋と具体策
サイバーエージェントグループのAI Shiftが共有する実践知
この記事は参考になりましたか?
- AIエージェントとの120日間~協働から見えた成功と失敗のリアル~連載記事一覧
- この記事の著者
-

株式会社AI Shift AIエージェント事業部 チーフエバンジェリスト 及川信太郎(オイカワ シンタロウ)
新卒で株式会社サイバーエージェントに入社。AIコールセンター領域でチャットボット・ボイスボットのセールスリーダーを担当後、プロダクト設計およびCS業務を担う沖縄対話センターの責任者を経て、現在はAIエージェントの導入・活用推進をリード。約90,000人への生成AIリスキリングを講師としても提供。Xはこちら(https://x.com/cyber_oikawa)
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です