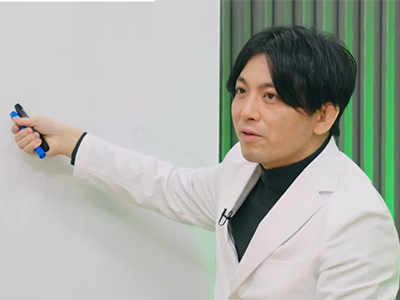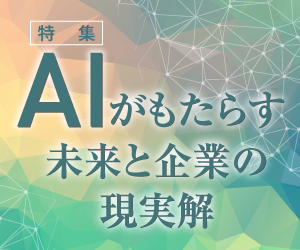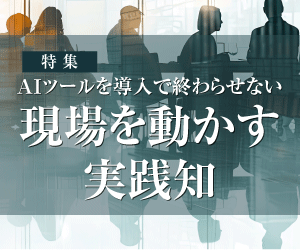会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

京部康男(AIdiver編集部)(キョウベヤスオ)
ライター兼エディター。翔泳社EnterpriseZineとAIdiverには業務委託として関わる。翔泳社在籍時には各種イベントの立ち上げやメディア、書籍、イベントに関わってきた。現在はフリーランスとして、エンタープライズIT、行政情報IT関連、企業のWeb記事作成、企業出版支援などを行う。Mail ...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です