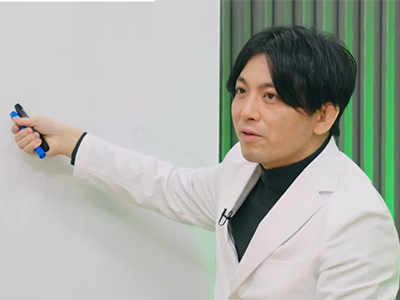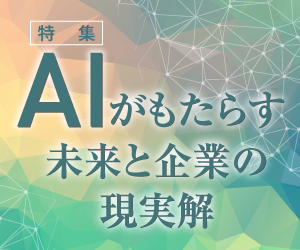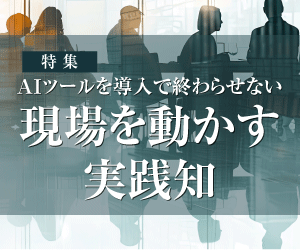目指すは国内EC流通総額10兆円 AIで実現する新しい買い物の形
会長である三木谷氏の「No AI, No Future」という強力なメッセージのもと、大規模なAI活用を進めている楽天グループ。中核事業の「楽天市場」を含むEC関連事業において、現状の約2倍にあたる国内EC流通総額10兆円を目指す。その鍵を握るのが、AIだ。
楽天市場はBtoBtoCのビジネスモデル。AIで顧客と企業の両方にメリットを生めるかが、今後の成長を大きく左右する。具体的には、AIが買い物のパートナーになるという。また、楽天市場に出店する5万以上の店舗に対しても、同社がAI活用を促すことで売上増を後押しする。
「この1~2年でAIはかなり進化しましたが、日本はまだまだ活用が進んでいないと感じています。単にAIを導入すれば売上が伸びるわけではありませんが、これからのEC展開において重要であることは間違いありません」

楽天グループは、OpenAIのような大手AI企業と戦略的パートナーシップを築いてきた。その一方で、日本語LLM(大規模言語モデル)を独自開発している。今年2月に提供を開始したLLM「Rakuten AI 2.0」には、特定の分野に特化した複数のサブモデル(エキスパート)によって、少ない計算量で高度な推論を可能にするMixture of Experts(MoE)アーキテクチャを採用した。小林氏は「当社の事業に特化した大規模言語モデル(LLM)も必要だ」と語る。
「当社では、多様なサービスを通じて多くの顧客データを保有しています。セキュリティやプライバシーの観点から、データの取り扱いにはセンシティブです。また、データの安全性の担保と日本固有のニーズに応えた柔軟な活用を両立するため、既存のAI企業と連携すると同時に、AI基盤の内製化も進める方針です」
この独自LLMも含め、同社が様々なLLMや小規模言語モデル(SLM)から最適なAIモデルを選択・導入し開発したのが、エージェント型AIツール「Rakuten AI」だ。楽天グループが提供するサービスを横断して、顧客と対話しながら商品などを提案する同ツール。既に楽天モバイル契約者専用のコミュニケーションアプリ「Rakuten Link」に搭載されており、楽天市場へは今秋に導入される予定となっている。
これにより、顧客がエージェントに曖昧な指示を出しても、AIが意図を汲んでマッチする商品を提案するといった体験が間もなく実現できるようになる。小林氏は「キーワード検索に頼らない、より自然な会話での商品探しが主流になっていく」と強調した。
「かつては『カテゴリ別ディレクトリサービス』が主流でした。通販なら、ユーザーが興味のあるカテゴリを階層的に掘り下げていくと、商品ラインアップが閲覧できる仕組みでした。それが、検索エンジンの台頭によって、商品の探しやすさが格段に上がりました。今、EC業界では当時と同じようなUIの大きな変更が起ころうとしているのです」