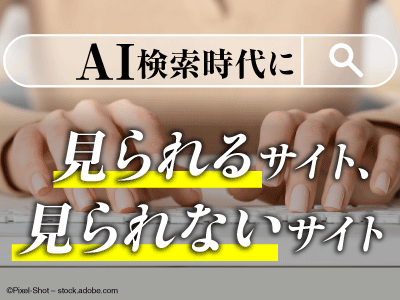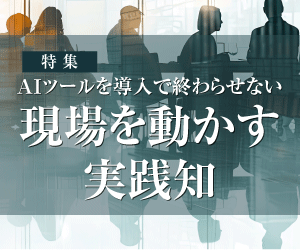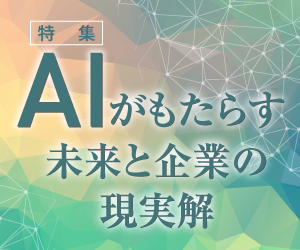「人間の仕事はなくならない」は本当か 日本に合ったAIとの共存の形
「AI時代」といわれる中、多くの人が人間ならではの価値にフォーカスしはじめているのではないだろうか。AIに仕事を奪われることはない──。そんな希望に満ちた声も聞こえてくる。一方で、海外企業がエンジニアを大量解雇したというニュースを目にするようになった。AIが人間を代替し得る時代が到来し、誰もが期待と不安を抱えているはずだ。
そのような状況下で、PKSHA Technologyは「人とソフトウエアの共進化」を掲げている。AIソリューション事業を手掛ける佐野長紀氏は、「AIはどこまでいっても完璧ではない」と語る。
「世の中で起こる事象、たとえば詐欺や誹謗中傷の手口も、常に新しいものが生まれますよね。一度作られたAIが、それらに完璧に対応し続けられることは、基本的にありません。AIが出した結果を人間が調整し、そこからAIがさらに賢くなる。AIが賢くなれば、人間はより新しい観点を得られる。そして、またAIにインプットする。キャッチボールを繰り返すように、人間とAIがともに進化していくのが基本的な形だと考えています」
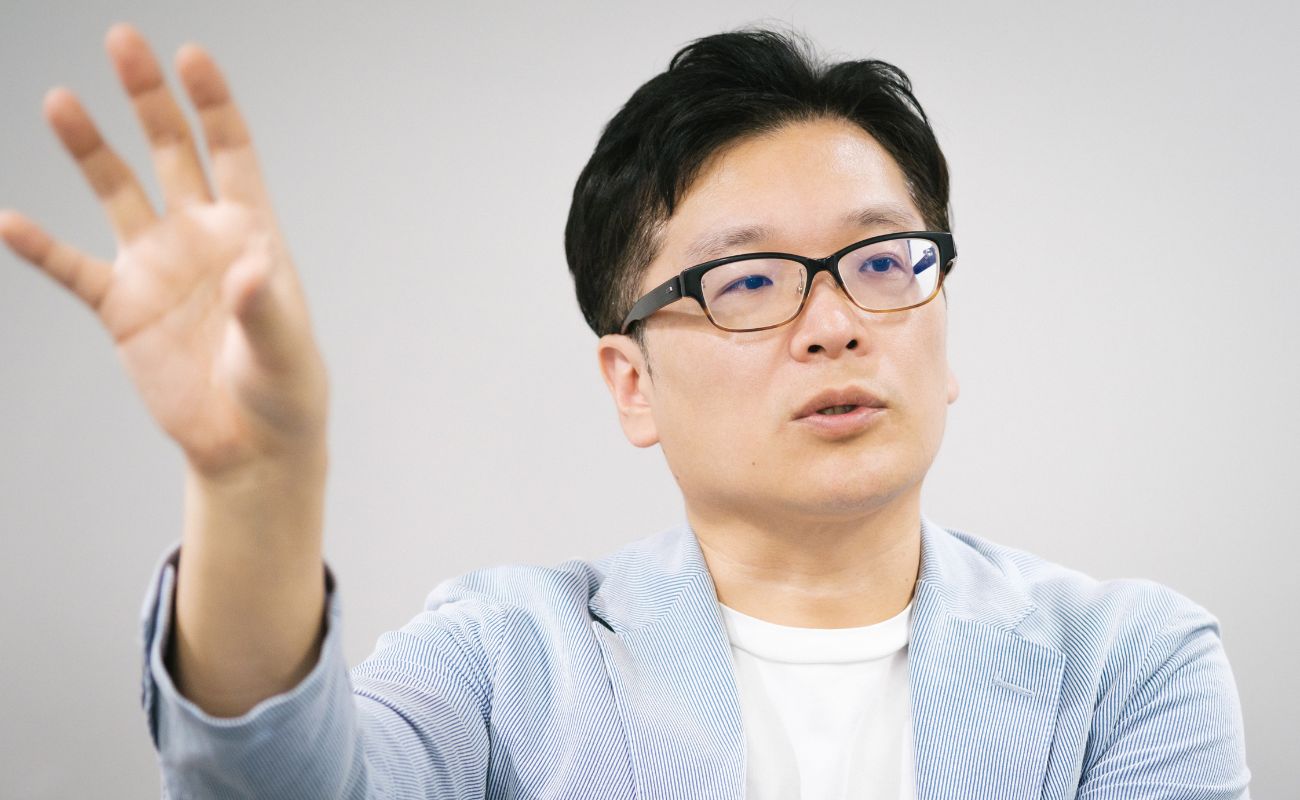
こうした共進化の考え方は、「日本の社会や文化とも親和性が高い」と佐野氏は説明する。理由の一つは、労働に関する法律や法令によって、簡単には人を解雇できない点が挙げられる。これに加えて注目したいのが、文化的な背景だという。
「当社の代表である上野山(勝也氏)が、よくいうんです。『人間』という字が『人の間』と書くように、日本では人と人をどうつなぐかを重視する文化が、根付いているように感じています。そのため、AIもまた、主役になるのではなく人と人、人とモノをつなぐ架け橋になるのではないでしょうか」
だからといって、もちろん現状維持で良いわけではない。大規模な置き換えは起こらずとも、一部の業務をAIに任せる企業が増える中、採用数の減少などは発生するだろう。佐野氏は「エンジニアであれば、ビジネスのノウハウと技術を掛け算できる“新しいタイプ”が選ばれるようになる」と強調する。
すなわち、開発の技術ではなく、ノウハウやそれらを組み合わせる洞察力、判断力がより重視される。これは、ビジネスパーソン全般にいえることだ。
「今まで、データ収集、加工、分析、意思決定という流れで行ってきた経営的な判断も、前半の作業はAIに任せられます。その後のアウトプットを見てどう判断するのかが、人間が担うべき部分。意思決定には、企業のスタンスが表れるからです」
それを理解してAIをうまく使えば、企業の意思決定の精度とスピードは上がると考えられる。ところが、AIを導入したものの活用しきれない、むしろ業務が増えたという事例は少なくない。何がハードルとなっているのだろうか。