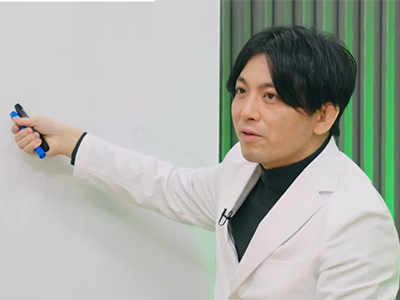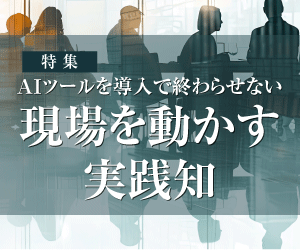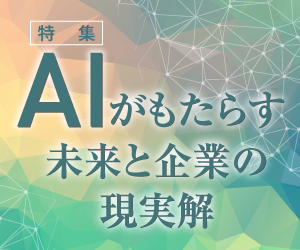大胆な目標を掲げた理由と超高速な技術進化への向き合い方
押久保:AIオペレーション室(※)設立のプレスリリースでは、「2026年までに社内のオペレーション業務を6割削減する」と表明されていましたよね。立ち上げ直後に具体的な数値を出されていて、驚きました。目標をまず掲げ、それを公表しやり切るのが御社らしい文化で、他社との違いだと感じます。目標達成に向けた感触はいかがでしょうか。

2011年サイバーエージェント新卒入社。生放送配信サービスの「FRESH LIVE」やコスメのクチコミサービス「Lulucos」など、入社後幅広いドメインに渡り、PMとして複数のメディア立ち上げを経験。女性活躍推進プロジェクト「CAramel」の幹部としても立ち上げから4年間活動。
上野:2023年10月の設立時に3ヵ年計画を立てており、この9月で2年目が終わります。1年目はゼロからのスタートで成果も出やすかったのですが、2年目は大きな課題に革新的に挑まないと前に進まないフェーズで苦戦しました。今は仕込みの期間を経て、3年目に数字を出すための活動を本格化させています。
設立時に掲げた「業務を6割削減する」という目標ですが、積み上げで届く数字ではありません。この「6割」という数字には、単にAIの使い方を改善するというレベルではなく、業務自体を再構築する必要があるというメッセージも込められています。
押久保:技術の進化によってできることの幅が広がった結果、計画の見直しが必要になることもありますよね。舵取りが難しいと思います。
上野:はい、常に計画を練り直しています。1年かけて試行錯誤していたことが、新しいモデル(AIの基盤技術)の登場によって、あっという間に解決できたこともありました。弊社のエンジニアが冗談で「この1年間、漫画でも読んで待っていればよかった」と話すほど、技術進化のスピードは速いです。この状況に向き合うには、開発者も含め、曖昧な状況を楽しめるマインドセットが不可欠だと感じています。
野口:その発言は状況を的確に表していますね。毎回本気で取り組むものの、すぐにゲームチェンジが起きて競技そのものが変わる。これまでやってきたことをちゃんと認めて、なおかつそれと違う新しい種目になっても受け入れる、という文化がないと、きつくて落ち込んでしまいます。こうした状況では状況の変化を的確に把握し、素早く適切な判断・行動ができる能力、すなわちアジリティが重要になりますね。
※
AIオペレーション室とは、サイバーエージェントの全社を挙げた生成AI活用を推進する専門組織。全社員の生成AIに関するリテラシー向上や、生成AIの業務活用に向けた環境整備、新たな価値創出に取り組んでいる。設立時のプレスリリースでは、現在のオペレーション業務を2026年までに6割削減することを表明した。
今できることではなく「AIの最大限」を見極める
押久保:AIの組織への浸透についてはどうでしょうか。先ほど野口さんから「アジリティ」という言葉が出ましたが、組織浸透を進める側も、方針を踏まえて活用する側も、状況が変わることを前提にするというマインドセットが必要ですよね。御社ではどのように取り組まれているのでしょうか。
上野:まず、「AIは最大限ここまでできるようになるだろう」という目線で業務を再構築し、その上で「では、現時点ではどこまでできるのか」を検証する考え方を取り入れています。AIが追いつくまでは人間が補完しつつ、徐々に人間の役割を減らしていくというアプローチです。「今はできないから」と切り捨ててしまうと、半年後にできるようになったときに大きな機会損失になってしまいます。
リテラシー教育も重視しています。全社員向けの研修から始めましたが、一度では浸透しません。楽しく学べる動画を用意したり、現場でAIを活用している社員を人づてに探してきて、勉強会を開いたりしています。同じ業務の仲間が事例を示すと「自分もできるかも」と感じてもらいやすいのでおすすめです。
野口:業務プロセスのAI化とリテラシーの底上げを両輪で回すのは、非常に重要ですね。AIオペレーション室には、幹部人材が正式にアサインされていますよね。会社としての意思決定を示すとてもユニークで素晴らしい取り組みだと思います。幹部の方々のAIへの取り組み姿勢はいかがですか。
上野:兼務している幹部たちは、自分で徹底的に使いこなすということよりも、組織にどう落とし込むかということに重きを置いています。ただ、事業責任者のAIに対する解像度が高いほうが活用は進みやすいですし、実際に良い使い方をしているなと感じますね。
野口:御社はトップダウンとボトムアップの両方が機能していますよね。トップが「AIは重要だ」と旗を振り、あとは各部門に任せている印象があります。
上野:おっしゃる通りです。「この2~3年が勝負だ」というメッセージを、最初にトップが出して、あとのやり方は各事業部やグループ各社に任せるというのが基本です。