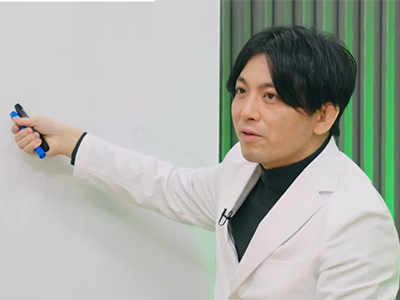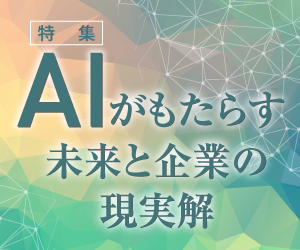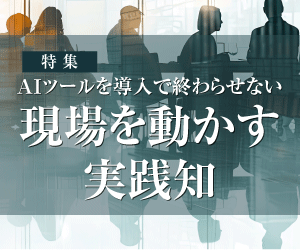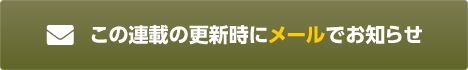会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
「前提が日々変わる状況を楽しむマインドが不可欠」サイバーエージェントから学ぶAX推進の舞台裏
サイバーエージェント 上野千紘×AIdiver特命副編集長のぐりゅう対談
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

こまき あゆこ(コマキ アユコ)
ライター。AI開発を行う会社のbizdevとして働きながら、ライティング業・大学院で研究活動をしています。 連絡先: komakiayuko@gmail.com
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です