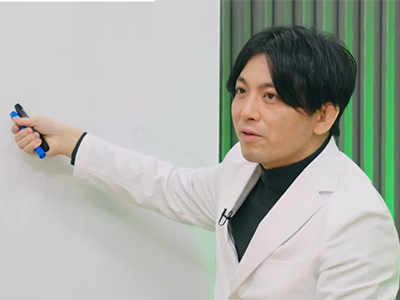開発の「民主化」がもたらすビジネスへの破壊力
――今回は、昨今広がりつつあるバイブコーディングをテーマに、野口さんも交えてお話を聞いていきます。開発現場でAI駆動開発やバイブコーディングといった言葉が飛び交うようになっていると思いますが、こうした変化をお二人はどう捉えていますか?
柴山:端的に言うと、開発の民主化が起きていると見ています。かつてExcelのマクロがビジネス現場に浸透した時と同じような流れではありますが、アウトプットの質や量、適用範囲は段違いになるインパクトを今感じています。特に、生成AI自体を組み込んだアプリケーションを、専門エンジニアでなくても、あるいは専門外の領域であっても「思い通りに、素早く」作れるようになったことは、ビジネスにおいて極めて破壊力があります。
野口:システム開発の発注という概念自体が、今後激減していくでしょうね。スモールからミドルクラスのユースケースであれば、仕様さえ言語化できれば、AI駆動開発やバイブコーディングによって、アプリケーションやAIエージェントすら自前で構築できますから。

――『AIdiver』としても、この大きなトレンドを深掘りしたいところです。そもそもAI駆動開発とバイブコーディングは、どう定義されるのでしょうか。
柴山:私の認識では、プロのエンジニアが、要件定義・設計、コーディングやレビュー・テストなどの従来のプロセスをAIで効率化していくのがAI駆動開発。対して、エンジニア・非エンジニアを問わず、特定の要件を満たすためにAIベースでアプリ自体を生成していくことをバイブコーディングと呼んで区別しています。
野口:私は「AIコーディング」という言葉で抽象度を上げて語ることが多いですが、柴山さんがおっしゃる通り、開発プロセスの改善なのか、それとも要件そのものを即座に形にするかという「深さと速度」の違いは明確にありますね。
宣言系言語での「取って出し」と基幹システムのジレンマ
――博報堂DYグループ内では、実際にどの程度のタイミングからこうした手法を取り入れているのでしょうか。
柴山:AI駆動開発については、GitHub Copilotが登場した約2年前から積極的に取り組んでいます。特にテラフォーム(Terraform)のような宣言系言語(※)における生産性改善は、すさまじいものがあります。論理構成が明確なため、AIの生成物をそのまま“取って出し”で使えるシーンが多く、エンジニア不足を補う大きな武器になっています。
野口:宣言系は言語モデルとの相性が抜群に良いですよね。コードの保守性や可読性を人間が担保しつつ、記述自体はAIに任せるというスタイルが定着しています。
――その一方で、バイブコーディングの活用はどのような背景で進んでいるのですか?
柴山:ここには「基幹システムのジレンマ」が関係しています。前回ご紹介した、我々が開発してきた「iPalette」などは強力な基幹システムですが、多くのクライアント企業に適用できる最大公約数的な機能提供が特徴です。最大公約数に含まれない、特定の広告主や特定の業界にだけ必要な尖った分析ツールを、一つひとつ年月をかけて開発することは時間、コスト、エンジニアリソースといったトータルの観点からみると、対応が難しい領域でした。
野口:そこをある程度諦めていたのが、今までのSaaSや基幹システムの常識でしたよね。業務をシステムに合わせてアジャストしていけば、一定の業務効率化が図れる、という。
柴山:そうですね。しかし、バイブコーディングであれば、これまでエンジニアをアサインできなかった「最大公約数から漏れた尖ったニーズ」に対して、数時間から数日という単位でアプリを開発できます。たとえるなら、1年で攻撃力100の武器を1個作るのではなく、攻撃力1の武器を100個作るような世界観です。
※
宣言系言語:「このような状態(結果)にする」と記述する形のプログラミング言語。プログラミング言語は、宣言系言語と、手続きやプロセスを順に指示する命令形言語の2つがある。
最速数時間で構築、特化型「TikTokトレンドチェッカー」の全貌
――実際にバイブコーディングで制作された具体例を教えてください。
柴山:バイブコーディングの事例でわかりやすいものとしては、昨年開発した「TikTokトレンドチェッカー」というアプリがあります。マーケティング現場では「今のトレンドを分析したい」というニーズが絶えませんが、各プラットフォームのAPIを叩いてシステムを構築するのは、本来なら非常に骨の折れる作業です。

野口:これ、UIも含めて本当に数日でできているんですよね?
柴山:はい。TikTokのAPIを活用させていただいて、例えば「美容業界の日本における直近1週間の急上昇タグ」を抽出し、それをさらにAIで分析して「なぜこれがトレンドなのか」を深掘りする。本来なら工数の関係で見送られてきたこうした特化型ツールを、エンジニアが数時間、重い制御を含めても1週間程度で形にしています。

TikTokのタグを利用してAIがトレンドを分析。本アプリはバイブコーディングにて短期間で開発
(クリックで拡大)

ハッシュタグ関連の動画を抽出することも可能。本アプリはバイブコーディングにて短期間で開発
(クリックで拡大)
――承認フローや開発のプロセスも、従来とは異なるのでしょうか?
柴山:今はまだ「バイブコーディングでの開発に向いている案件か」「知見が得られそうか」という観点で選別していますが、基本的には現場のニーズを即座に形にするスピード感を優先しています。
野口:組織として、自発的な試みだけでなく、プロダクト開発のロードマップの中にバイブコーディングを組み込んで、数字を通して管理している企業はまだ少ないです。これを「ビジネス」として実行している点は非常に早い意思決定だと感じます。
バイブコーディングだからこそ許容される制約と、AI活用のコツ
――デモを拝見すると、非常に実用的ですが、品質面での懸念はないのでしょうか?
柴山:正直に言うと、これらのシステムはエラーハンドリングも甘いですし、先ほど紹介したトレンドチェッカーでいいますと、キャッシュ保持もされないなど、デリバリーを優先した作りになっています。
エンジニアがプロの仕事として既存の手法で開発したシステムと比較すると、あり得ない品質かもしれません。しかし現場からすれば、その品質が犠牲になったとしても「今まで手に入らなかった情報が手に入る」というベネフィットが圧倒的に勝ります。
野口:AIを動かす前提のアプリなら、バイブコーディングの方が圧倒的に楽なんですよね。プロンプトの管理やモデルの呼び出し、フロントへの接続といった複雑な工程を、AIがよきに計らってパッケージングしてくれますから。ちなみにこの取材の音声をリアルタイムで認識させ、インフォグラフィックにするツールをバイブコーディングで自作して走らせるなども可能です。
――なんと! 可能性を実感させられますね。では、誰もがバイブコーディングを使いこなせるようになるためのハードルは何でしょうか?
柴山:現在はまだ、APIの制限への対応やデータベースの叩き方を知らないとリスキーな部分があるため、エンジニア主導で行っています。しかし、最大のボトルネックはそこではなく「要件をいかにディテールまで言語化できるか」です。
野口:同感です。ビジネスの文脈で「何の機能が、誰のために、どうあるべきか」をしっかり記述できる力ですね。AIが賢くなった分、指示が曖昧だと曖昧なままのアプリが内在化してしまいます。言葉をきちんと扱う、つまりロジカルに言語化できる企業こそが、バイブコーディングにおいて強くなります。
経営者がバイブコーディングを行うべき理由
――AIが進化するほど、言語化力の重要度が増す、と。
野口:それに関連すると、私はやはり、経営者の方が直接AIコーディングを扱うべきだと思っているんです。経営会議に出ながら、その場で実行仮説をアプリという形でアウトプットできる人は、戦略と実行の両輪を握る最強の経営者になり得ます。「これを作っておいて」と指示するのではなく、「これ作ってみたけどどうだ?」というトップダウンの在り方に変わるはずです。

柴山:今の野口さんの例は、まさに理想的です。経営者から現場への指示というものは、往々にしてハイコンテキストで抽象的になってしまうものですが、その行間を埋めるためにパワポを作るのではなく、動くツールを作って見せる。会議をグラフィックレコーディングするような感覚で、アプリケーションを提示して意思疎通のズレを解消する。これは、会議中のコミュニケーションを激変させる可能性を秘めています。
――クライアントワークにおいても、そうした「具体化のスピード」は価値になりますか。
柴山:広告会社はもともと、クライアント企業の抽象的な思いを形にするのが仕事です。それが言葉や企画書だけでなく「ツール」という形でも示せるようになる。イメージが違う、ブランドっぽくない、といった不一致を即座に埋めるドリルとしても、バイブコーディングは機能すると考えています。
野口:クライアント企業側の経営分析アプリをその場で作ってしまうような、「クライアントサイド・バイブコーディング教室」のようなソリューションも十分にあり得ますよね。
「ONE-AIGENT」が目指す、余白なきマーケティングの未来
――バイブコーディングの浸透は、マーケターのスキルセットも変えていくのでしょうか。
柴山:スキルセットというより、労働時間やコストといった物理的限界を拡張するものになると思います。情報も、分析軸も手に入れられるようになった上で、いかに広告としてクライアント企業に提供できるかが、今後の肝になるでしょう。
加えて、手法を学ぶより、問いを立てる力がますます重要になります。手法だけ学んでも、作りたいものや解決したいイシューがないと、生成AI時代の道具は宝の持ち腐れです。社員一人ひとりが「このデータを掘り起こせば、新しい価値が出るのではないか」という問いを持てるかどうかが試されています。
野口:物理的な突破というのは、非常に重要な視点だと思います。本当は大切なのに、人間が今まで扱いきれないと捨ててきたり、蓋をしてきたりした情報は膨大にあるはずです。バイブコーディングは、それを掘り起こすのに機能する“発掘耒”になり得ます。
――最後に、このバイブコーディングの流れが「ONE-AIGENT」の構想とどう接続していくのか教えてください。
柴山:本取り組みは、最大公約数から漏れた「ビジネスの空白」を埋めるために機能させていきます。特定のツールを売るのではなく、エージェンティックな仕組みを駆使して、マーケティングのあらゆる余白を埋めていく。その先に、広告主と我々のエージェント同士が会話をし、お互いのバイブコーディングによって生まれた知見を交換し合うような世界が来るでしょう。
野口:とても興味深いお話でした。BtoBにおける空白をAIで埋める作業は、最終的に消費者の満足度というBtoCの価値につながっていくはずです。ベースとなる強力なデータ基盤の上に、バイブコーディングという機動力の高いインターフェースが乗ることで、マーケティングの精度は極限まで高まると確信しています。
ONE-AIGENTに関するお問い合わせはこちらから
本サービスに関するご不明点やご相談はHakuhodo DY ONEのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。