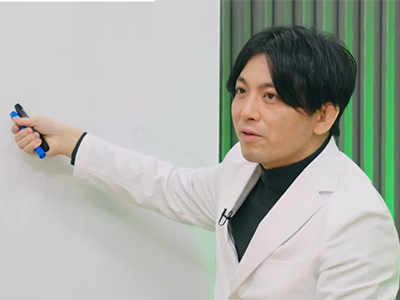開発の「民主化」がもたらすビジネスへの破壊力
――今回は、昨今広がりつつあるバイブコーディングをテーマに、野口さんも交えてお話を聞いていきます。開発現場でAI駆動開発やバイブコーディングといった言葉が飛び交うようになっていると思いますが、こうした変化をお二人はどう捉えていますか?
柴山:端的に言うと、開発の民主化が起きていると見ています。かつてExcelのマクロがビジネス現場に浸透した時と同じような流れではありますが、アウトプットの質や量、適用範囲は段違いになるインパクトを今感じています。特に、生成AI自体を組み込んだアプリケーションを、専門エンジニアでなくても、あるいは専門外の領域であっても「思い通りに、素早く」作れるようになったことは、ビジネスにおいて極めて破壊力があります。
野口:システム開発の発注という概念自体が、今後激減していくでしょうね。スモールからミドルクラスのユースケースであれば、仕様さえ言語化できれば、AI駆動開発やバイブコーディングによって、アプリケーションやAIエージェントすら自前で構築できますから。

――『AIdiver』としても、この大きなトレンドを深掘りしたいところです。そもそもAI駆動開発とバイブコーディングは、どう定義されるのでしょうか。
柴山:私の認識では、プロのエンジニアが、要件定義・設計、コーディングやレビュー・テストなどの従来のプロセスをAIで効率化していくのがAI駆動開発。対して、エンジニア・非エンジニアを問わず、特定の要件を満たすためにAIベースでアプリ自体を生成していくことをバイブコーディングと呼んで区別しています。
野口:私は「AIコーディング」という言葉で抽象度を上げて語ることが多いですが、柴山さんがおっしゃる通り、開発プロセスの改善なのか、それとも要件そのものを即座に形にするかという「深さと速度」の違いは明確にありますね。
宣言系言語での「取って出し」と基幹システムのジレンマ
――博報堂DYグループ内では、実際にどの程度のタイミングからこうした手法を取り入れているのでしょうか。
柴山:AI駆動開発については、GitHub Copilotが登場した約2年前から積極的に取り組んでいます。特にテラフォーム(Terraform)のような宣言系言語(※)における生産性改善は、すさまじいものがあります。論理構成が明確なため、AIの生成物をそのまま“取って出し”で使えるシーンが多く、エンジニア不足を補う大きな武器になっています。
野口:宣言系は言語モデルとの相性が抜群に良いですよね。コードの保守性や可読性を人間が担保しつつ、記述自体はAIに任せるというスタイルが定着しています。
――その一方で、バイブコーディングの活用はどのような背景で進んでいるのですか?
柴山:ここには「基幹システムのジレンマ」が関係しています。前回ご紹介した、我々が開発してきた「iPalette」などは強力な基幹システムですが、多くのクライアント企業に適用できる最大公約数的な機能提供が特徴です。最大公約数に含まれない、特定の広告主や特定の業界にだけ必要な尖った分析ツールを、一つひとつ年月をかけて開発することは時間、コスト、エンジニアリソースといったトータルの観点からみると、対応が難しい領域でした。
野口:そこをある程度諦めていたのが、今までのSaaSや基幹システムの常識でしたよね。業務をシステムに合わせてアジャストしていけば、一定の業務効率化が図れる、という。
柴山:そうですね。しかし、バイブコーディングであれば、これまでエンジニアをアサインできなかった「最大公約数から漏れた尖ったニーズ」に対して、数時間から数日という単位でアプリを開発できます。たとえるなら、1年で攻撃力100の武器を1個作るのではなく、攻撃力1の武器を100個作るような世界観です。
※
宣言系言語:「このような状態(結果)にする」と記述する形のプログラミング言語。プログラミング言語は、宣言系言語と、手続きやプロセスを順に指示する命令形言語の2つがある。